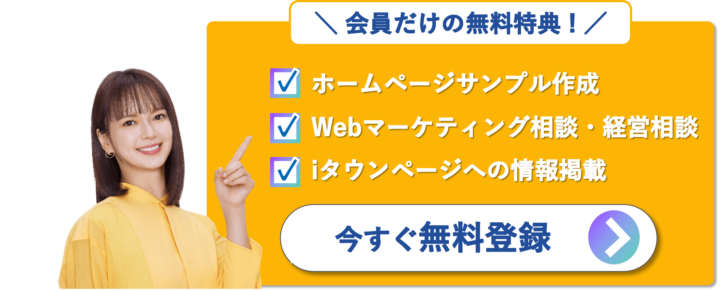ゼロクリック検索という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
知りたい情報を入手するために、スマートフォンなどで検索エンジンを使って調べるという行為は、もはや私たちの日常生活にかなり深く浸透している行動です。
ゼロクリック検索とは、検索エンジンで情報検索した際に、検索結果ページ上で必要な情報が得られるため、ウェブサイトにアクセスすることなく検索を完結する現象を指します。
みなさんも、検索結果ページ上に知りたかった情報が表示され、そのまま画面を閉じたという経験があるのではないでしょうか。
ユーザーにとっては、より早く情報を入手できてとても便利ですが、企業にとってはウェブサイトにアクセスしてもらえなくなるという、無視できない課題が発生しています。今回は、このゼロクリック検索の詳細から、対策方法まで、詳しく解説します。最近自社ウェブサイトへの流入が減ったな・・・とお悩みのあなた、ぜひご一読ください。もしかしたらその一因がわかるかもしれません。
ゼロクリック検索とは
前述したように、ゼロクリック検索とは、検索エンジンで情報検索した際に、検索結果ページだけで必要な情報を得て、その先のウェブサイトにアクセスすることなく検索行動を終了してしまうことです。例えば、検索エンジンで「大阪の天気」と検索すると、検索結果の最上部に大阪の今日の天気や週間天気予報が表示され、わざわざ天気予報サイトにアクセスしなくても欲しかった天気の情報を入手できます。また、わからない単語の意味を知ろうと検索した時にも、検索結果に辞書的な説明が表示され、辞書サイトに移動することなく単語の意味を知ることができます。各業界の専門用語を検索した際にも、いくつかのサイトの内容を抜粋するかたちで、簡潔にその用語の意味をまとめた文章が表示され、その用語について詳しく書かれたウェブサイトにアクセスしなくても概要がわかるのです。
ゼロクリック検索が増えた背景
ゼロクリック検索の増加には、ユーザーの行動変化と検索エンジンの進化が深く関わっています。
検索結果を早く知りたいユーザーの心理
現代のユーザーは、必要な情報を迅速に得たいと考えています。特にスマートフォンなどの普及が進むにつれ、ユーザーは時間をかけずに回答を得られる検索体験を期待するようになりました。「いつでも」「どこでも」「すぐに」が当たり前な環境になっているのです。この「検索結果を少しでも早く知りたい」というユーザーの心理がゼロクリック検索の増加につながっているのです。
検索エンジンの進化
Googleなどの検索エンジンは、ユーザーにとって便利な情報提供を重視しており、検索ユーザーのニーズを満たすため、日々検索エンジンの改善に努めています。その結果、検索結果ページでサイトの概要やユーザーのレビューなどが確認できる「リッチスニペット」や検索ワードに関連する情報を検索エンジンの右側に表示させる「ナレッジグラフ」、ユーザーが求めていたと思われる情報を検索結果の最上部に強調表示する「強調スニペット」などの機能が追加されました。これにより、検索ユーザーがウェブサイトを訪れる手間を省き、求めている情報を素早く検索ユーザに提供することが可能になったのです。
ゼロクリック検索が企業に及ぼす影響
ゼロクリック検索は、ユーザーにとっては便利ですが、ウェブサイトを運営する企業側にとっては新たな課題を生み出すこととなりました。
ウェブサイトへのトラフィック減少
ゼロクリック検索の増加による影響として、真っ先に考えられるのは、ウェブサイトへのアクセス数の減少です。
ユーザーはウェブサイトのリンクをクリックしなくても求めていた情報が手に入れるため、せっかく検索結果の上位に表示されても、リンクがクリックされないケースが増え、アクセス数の減少につながります。また、アクセス数が減少することで、成果につながる機会も減少し、記事がシェアされる機会も減ってしまいます。
ブランディングの機会の減少
ゼロクリック検索の増加によってウェブサイトへの訪問者が減ると、企業が自社のブランドメッセージや詳細な情報を伝える機会も減ってしまいます。
検索結果ページに表示される情報は限られているため、企業が他社と差異化するためのスペースが少なくなります。特に、強調スニペットやナレッジパネルに表示される情報は簡潔であるため、詳細なブランドストーリーなどを伝えることが難しくなります。
これまでは、ユーザーがウェブサイトに訪れることで、企業のブランドカラー、コンテンツなど、直接的なブランド体験を提供することができました。しかし、ゼロクリック検索では、検索結果画面で必要な情報が得られてしまい、ウェブサイトに訪れる機会が減ってしまうため、ブランドとの深いつながりを築くことが難しくなります。特に新規顧客にとって、検索結果画面で企業名を見るだけでは、ブランドに対する強い印象や認知度を形成することは困難です。ウェブサイトに訪れてもらって初めて、企業の強みや特徴、製品・サービスの魅力を深く理解してもらうことができます。このため、ゼロクリック検索はブランド認知度の低下にも影響を及ぼすことになるのです。
ゼロクリック検索への対応策
検索エンジンはユーザーの利便性を重視しているため、ゼロクリック検索が増えるのは自然な流れです。しかし、ゼロクリック検索によるウェブサイトへのアクセス減少は明らかで、ウェブサイトを運営する企業側もこの変化に適応し、ユーザーの興味を引く工夫が必要です。
では、ゼロクリック検索の時代にウェブサイト運営者はどのように対応すれば良いのでしょうか。ここからは、ゼロクリック検索への対応策をいくつかご紹介します。
強調スニペットへの表示を意識する
強調スニペットとは、検索結果の一番上(広告を除く)に表示される、検索ワードに対する簡潔な答えのことです。ユーザーはわざわざウェブサイトに訪れなくても、検索結果画面だけで必要な情報を得ることができます。この強調スニペットに表示できれば、ユーザーに自社サイトをアピールすることができます。強調スニペットはユーザーが検索するワードに対し、適切な回答をしているウェブサイトの回答部分を抜粋して表示しています。このため、強調スニペットに表示されているということは、検索エンジンが、あなたのウェブサイトの情報を信頼できるものと判断している証となり、信頼性が向上します。
強調スニペットへの表示を意識する具体的な方法としては、以下のようなものがあります。
検索意図を正確に捉える
ユーザーがどんな言葉で検索するかを予測し、その意図に合った情報を提供します。
例えば、「横浜観光」というキーワードで検索するユーザーは、観光スポットや交通手段など、具体的な情報を求めていると考えられます。ユーザーの検索意図にあった情報を提供するようにしましょう。
簡潔で分かりやすい文章にする
検索結果に表示される文字数には制限があります。
重要なキーワードを含めつつ、簡潔に、そしてユーザーが求めている答えを的確に伝えましょう。
構造化データの活用
構造化データとは、検索エンジンがウェブサイトの内容をより正確に理解できるようにするためのマークアップです。構造化データを導入することで、強調スニペットに表示される可能性を高めることができます。
リスティング広告を出稿する
リスティング広告とは検索結果ページの上部に表示される広告のことで、SEOでの検索結果や強調スニペットの表示よりも上部にサイトを表示できます。
つまり、広告にお金をかけて強調スニペットの表示よりも上位に表示することができれば、ゼロクリック検索の影響をあまり受けずにアクセスしてもらえる可能性が高くなるわけです。
もちろん広告出稿にはコストがかかりますし、同じような考えの企業がたくさんいれば、それだけ広告費も高くなってしまいます。利用する場合は自社のリソースや予算などをよく考える必要があります。
クリックしたくなるようなタイトルをつける
検索結果画面から自社のコンテンツやページにアクセスしてもらうためには、タイトルをクリックしてもらう必要があります。そのため、クリックしたくなるようなタイトルをつけることができれば、ゼロクリック検索の影響を受けにくくなります。
ゼロクリック検索で解決できるのは一問一答のような簡潔な答えでも足りるようなものであり、悩みが深い疑問などでは、入口部分しか解決できません。そのため「この記事を読めばもっと詳しい情報が分かって解決できそう」と思わせるようなタイトルをつけるようにしましょう。
ゼロクリック検索をしているユーザーも、他に自分に役立ちそうな情報がないと判断してしまい、検索行動を終了している場合もあります。自分の悩みや不明なことを解決してくれそうだと思われるようなタイトルをつけることでゼロクリック検索で終了せずに、その先のウェブサイトへのアクセスも見込めるでしょう。
ゼロクリック検索は、ユーザーにとっては迅速かつ便利な情報取得手段ですが、企業にとってはウェブサイトへのアクセス減少やブランディング機会の減少といった課題をもたらします。これに対応するためには、強調スニペットへの表示を意識したコンテンツ作成や、リスティング広告の活用、クリックしたくなるようなタイトルの工夫が重要です。ゼロクリック検索の時代においても、ユーザーに価値ある情報を提供し続けることで、企業の存在感を維持し、ブランド認知度を高めることは可能です。ぜひ、これらの対策を実践し、ゼロクリック検索の影響を最小限に抑えましょう。
NTTタウンページが運営する「Myタウンページ」では、忙しい個人事業主や中堅・中小企業のビジネスオーナーさまのお悩み解決をサポートする無料サービスを提供しています。
専門知識を持つ資格保有者(ウェブ解析士、SEO検定1級)へのWebマーケティング相談※1の窓口を設けており、デジタルだけではなくこれまで紙媒体の電話帳(タウンページ)を発行してきたノウハウもございますので、適切なPR手段や集客に関することなど、Webマーケティング全般についてご相談いただけます。
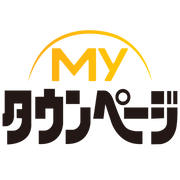
他にも経営の専門家(経営コンサルタント、起業コンサルタント(R)、ファイナンシャルプランナー、(CFP(R)、一級ファイナンシャル・プランニング技能士)、中小企業診断士、司法書士、行政書士、税理士、特定社会保険労務士等の資格保有者)に相談できる経営相談先紹介サービス※2、Webマーケティングや経営に役立つ新鮮かつ正確な情報をわかりやすく解説したコラム・動画コンテンツなど、充実の特典をご利用いただけます。
無料会員登録をいただくだけで、ビジネスオーナーさまのお仕事の強い味方になりますので、まずはお気軽にご登録ください!
※1 相談時間は1回30分までで、利用可能回数は1会員につき月1回まで
※2 相談時間は1回30分までで、利用可能回数は1会員につき月3回まで
Myタウンページ会員登録は
簡単ステップ!
※iタウンページに店舗・企業の掲載がない場合は、こちらからお問い合わせください。
・Googleは、Google LLCの登録商標または商標です。
・各ルール、サイトの情報は2025年1月現在タウンページ社調べのものです。