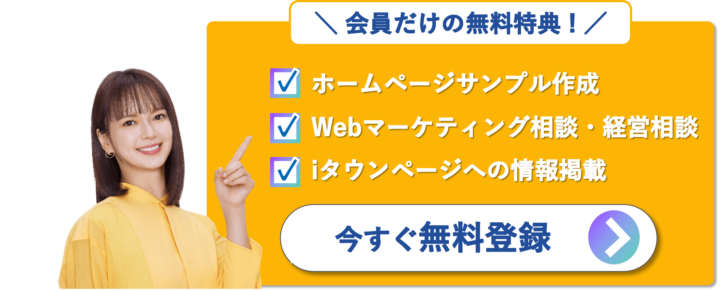最終更新:2025年3月
ウェブサイトのパフォーマンスを評価する指標にはさまざまなものがありますが、その中でも「直帰率」は特に重要な要素の一つです。
直帰率とは、訪問者が最初のページだけを見てサイトを離れてしまう割合のことで、この指標は、ウェブサイトがどれだけ効果的に訪問者を引き留め、興味を引き続けているかを測るバロメーターとなります。
このコラムでは、直帰率の基本的な意味や、直帰率が高くなる原因、そしてその改善方法について詳しく解説します。ウェブサイトの改善に取り組むためのヒントが欲しいとお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。
直帰率とは
直帰率とは
直帰率とは、ウェブサイトを訪れたユーザーが最初のページだけを閲覧して、すぐに他のサイトへ移動したり、ブラウザの「戻る」ボタンをクリックしたり、タブを閉じたりして、そのままウェブサイトから離脱した割合を指します。
直帰率は以下の計算式で算出できます。
直帰率(%)=直帰数÷全セッション数×100
例えば、あるウェブサイトに1日10件の訪問があったとします。このうち6件は最初のページを見た後にウェブサイト内の別のページへ移動し、残りの4件は他のページを見ることなくウェブサイトから離脱した場合、直帰率は「4÷10×100=40%」と計算できます。
直帰率はウェブサイトに訪れたユーザーの満足度を測る重要な指標です。極端に高い直帰率は、ユーザーの求めている情報ではなかったり、ウェブサイトに魅力を感じなかったりしている可能性が考えられます。
ただし、直帰率が高くても、1ページのみでユーザーの必要な情報をすべて得られているという場合もあります。そのため、「直帰率が高い=悪い」とばかりは言えないことも覚えておきましょう。
GA4での直帰率とは
前述したように、直帰率とは、ウェブサイトを訪れたユーザーが最初のページだけを閲覧して、そのままウェブサイトから離脱した割合を指しますが、現在ウェブサイトの分析ツールとして普及しているGA4(Google Analytics4)では、この直帰率の定義が異なるため注意が必要です。
GA4の直帰率は、「エンゲージメントのなかったセッションの割合」です。
GA4のエンゲージメントとは、以下の状態を指します。
- 10秒を超えて継続したセッション
- 2回以上のページビューまたはスクリーンビューが発生したセッション
- コンバージョンイベント(資料ダウンロードや購買行動など、サイト管理者が定義した指標)が発生したセッション
上記のいずれかに該当する場合は、ユーザーが最初の1ページをチェックしてそのまま離脱しても直帰とカウントされないので注意が必要です。
例えば、あるページに来訪して40秒滞在して離脱した場合、一般的な定義では、直帰と判定されますが、GA4の場合は10秒以上滞在しているため直帰とは判定されないことになります。
直帰率が高い原因
直帰率が高い場合、ユーザーがウェブサイトに対して不満を感じたり、期待に応えられていない可能性があります。
ウェブサイトの直帰率が高くなる原因はさまざまですが、それぞれの要因を見極め、適切な改善につなげることが大切です。
ここからは、直帰率が高くなる代表的な原因についていくつかご紹介します。
ユーザーの欲しい情報がない
直帰率が高い原因の一つは、ユーザーの欲しい情報がない、もしくは見つけられないからです。
例えば、ユーザーが検索エンジンの検索結果に表示されたタイトル名のリンクをクリックしてウェブサイトに訪問したとします。
この時に、検索結果に表示されていたタイトル名と異なる文言がファーストビュー(ユーザーがウェブサイトに訪れた時に最初に目に入る部分)に表示された場合、ユーザーは欲しい情報がないと判断してしまう可能性があります。欲しい情報がなければ、そのユーザーは別のウェブサイトへと移動してしまう可能性が高まるでしょう。このように、ユーザーの欲しい情報がファーストビューにないことが原因で、直帰率が高くなることがあります。
読み込み速度が遅い
直帰率が高い原因として、読み込み速度が遅いということも考えられます。
例えば、サイズが大きな画像や動画が埋め込まれていたり、不要な計測タブが設置されているページは、画像や動画が表示されるまでに時間がかかったり、計測タブの読み込み中の状況が続いたりします。
このようにウェブサイトのページ読み込みに時間が長くかかると、ユーザーはストレスを感じて、すぐにそのページから去ってしまう可能性が高まるでしょう。
このように、読み込み速度が遅いことが原因で、直帰率が高くなるケースもあります。
特にモバイルユーザーは、ページ読み込み速度に敏感なため、注意が必要です。
モバイル対応が不十分
スマートフォンの普及により、モバイル機器からのウェブサイトへの訪問が増えている近年では、モバイル端末の画面サイズに合わないデザインや表示崩れなどの問題も、直帰率を高くする原因となっています。
例えば、スマートフォンで閲覧した時に、文字が小さかったり、スマートフォンの横幅からコンテンツがはみ出るなどしてパソコン向けのデザインでページが表示された場合、とても見づらい状態になります。この場合、ユーザーはストレスを感じて、モバイル対応が十分な他のウェブサイトに移動してしまう可能性が高まるでしょう。
このように、モバイルユーザーにとって見づらいことが原因で、直帰率が高いということもあるのです。
ナビゲーションがわかりづらい
直帰率が高い原因として、ナビゲーションがわかりづらいということも考えられます。
例えば、グローバルメニューの項目がわかりづらかったり、フッターメニューやコンテンツ内のアンカーテキストなどの色が通常のテキスト文章と同じ色で見分けがつきづらい場合、ユーザーはウェブサイト内で迷い、欲しい情報になかなかたどり着けない状態になります。
ナビゲーションがわかりづらければ、ユーザーがリンクを見つけてクリックしづらくなり、その結果、ウェブサイト内の他のページに遷移せずに、別のウェブサイトに移動してしまう可能性が高まるでしょう。
このように、ナビゲーションがわかりづらいことも直帰率が高くなる原因の一つとなるのです。
こうした、ユーザーにとってストレスを感じる状況を回避する為に、直帰率を考慮して、ユーザー行動に配慮したサイト改善が必要になるのです。
直帰率の改善方法
直帰率を改善するうえでの基本は、ユーザーにとって価値あるコンテンツを提供し、ユーザーにとって使いやすいウェブサイトを構築することです。
ここからは、具体的な改善方法をいくつかご紹介します。
検索意図に合ったコンテンツを作成する
第一に、ユーザーのニーズに合った情報を提供することが大切です。
ユーザーは明確な目的を持って検索エンジンを利用しているため、その意図に応えられないページは「期待外れ」と判断され、直帰につながるのです。これを防ぐためには、ターゲットとなるユーザーの検索意図を正確に理解し、それに合ったコンテンツを届けることが重要となります。
まず、ユーザーの検索意図を分析する際には、検索クエリが示す「情報取得」「比較検討」「購入意欲」などの段階を把握することが必要です。
例えば、検索キーワードが「〇〇の使い方」の場合は、ユーザーは初心者向けの具体的な手順や図解を交えた説明などを求めていると考えられます。一方で、検索キーワードが「〇〇 比較」なら、製品比較やレビュー、ランキング形式のコンテンツなどが求められているものと考えられます。このように、検索意図に応じた情報を適切な形式で届けることで、ユーザーの期待に応えることができ、直帰の防止につながります。
また、ページ全体の構成にも注意が必要です。コンテンツをわかりやすく整理し、必要な情報がすぐに見つかるようにすることがポイントとなります。見出しや小見出しを効果的に活用して内容を階層化し、要点が一目でわかるデザインにすることで、ユーザーが求めている情報を発見しやすくなります。
ページの読み込み速度を速める
ページの読み込み速度は、ユーザーにとって「第一印象」を決定する重要な要素です。ページの表示速度が遅いと、ユーザーにストレスを与え直帰率が高くなる傾向にあります。ページの読み込み速度が遅くなる原因としては、ファイルサイズが大きい画像や動画、不要なスクリプトなどが挙げられます。
表示速度の改善には以下のような対策が有効です。
- 画像や動画ファイルを軽量化する
- HTMLやCSSなどのソースコードを簡潔化する
- サーバーの応答速度を改善する
また、読み込み途中でも主要なコンテンツを先に表示する「遅延読み込み(Lazy Loading)」を導入することで、ユーザーに素早く必要な情報を届けることが可能になります。
モバイル対応
モバイルファーストの現代において、あらゆるデバイスで快適に閲覧できるレスポンシブデザインの採用は、非常に重要です。
スマートフォンの利用者が増加する中、デバイスに応じてレイアウトやフォントサイズが自動的に調整される設計は、ユーザー体験の向上につながります。
モバイル対応が不十分な場合、スマートフォンの画面に収まりきらない要素や読みにくいテキストが原因でユーザーがウェブサイトを離れてしまう可能性が高まります。
また、モバイル環境では、指での操作が中心になるため、操作性の向上も重要となります。例えば、スマートフォンに最適化された大きさのボタンを設置することで、タップミスを減らし、ストレスのない操作感の実現が可能になります。
さらに、フォームデザインも簡潔で分かりやすくしましょう。入力項目を最小限に絞り、プルダウンメニューや自動補完機能を活用して、ユーザーがストレスなく入力を完了できる環境を整えます。
実際にモバイル端末を用いて、デザインやボタンの配置、テキストの見え方などの動作確認をすることも忘れないようにしましょう。
ウェブサイト内のナビゲーションをわかりやすくする
直帰率が高い原因のひとつとして挙げられるのが、ユーザーが必要な情報にスムーズにたどり着けないことです。ナビゲーションがわかりにくい場合、ユーザーはストレスを感じ、目的のページにたどり着く前に離脱してしまいます。
これを防ぐためには、明確で直感的なナビゲーション設計が必要です。
グローバルメニューには、例えば「製品情報」「料金プラン」「導入事例」など、具体的でわかりやすい名称を設定すると、ユーザーが求める情報を見つけやすくなります。
また、パンくずリストを導入することで、ユーザーは自分がウェブサイト内のどこにいるのかを視覚的に把握でき、次の行動をスムーズに行うことができます。
製品ページや料金ページの直帰率が高い場合は、CTAの配置やデザインを見直してみましょう。「資料請求ボタン」や「問い合わせボタン」が目立たない、または適切な位置に配置されていない場合、確度の高い見込み客を逃す恐れもあるのです。
この問題を解決するために、ヒートマップツールを活用してユーザーがどの部分を注視しているか、どこで行動を止めているかを分析することが効果的です。ヒートマップツールを利用することで、主観に頼らず、データに裏付けられた効果的な改善策を導く手助けとなります。そして、その結果にもとづいて、ボタンの色や文言を調整したり、スクロールしなくても見える位置に配置するなどの改善を行うことで、コンバージョン率の向上も期待できます。
さらに、ブログ記事や情報提供型コンテンツのページでは、内部リンクを活用して関連性の高いコンテンツにユーザーを誘導することも重要です。内部リンクを設置して、関連コンテンツや事例ページなどに誘導することにより、ユーザーが興味を持ったページに進みやすくなり、ウェブサイト内の回遊性が向上します。また、このようなリンク設置は、直帰率の低下だけでなく、ユーザーがサイトに信頼感を抱くきっかけにもつながるのです。
直帰率の改善は、単にユーザーをサイトに留めるだけでなく、信頼感やブランド価値の向上にもつながります。ユーザーにとって「必要な情報が得られる場所」であると感じてもらうことが、直帰率低下の最も効果的な施策といえるでしょう。
直帰率は、ウェブサイトのパフォーマンスを評価する上で非常に重要な指標です。高い直帰率は、ユーザーが求める情報を提供できていない可能性を示唆しますが、適切な改善策を講じることで、ユーザーの満足度を向上させることができます。検索意図に合ったコンテンツの作成、ページの読み込み速度の向上、モバイル対応の強化、わかりやすいナビゲーションの設計など、具体的な対策を実施することで、直帰率を効果的に改善し、ウェブサイトの価値を高めましょう。
NTTタウンページが運営する「Myタウンページ」では、忙しい個人事業主や中堅・中小企業のビジネスオーナーさまのお悩み解決をサポートする無料サービスを提供しています。
専門知識を持つ資格保有者(ウェブ解析士、SEO検定1級)へのWebマーケティング相談※1の窓口を設けており、デジタルだけではなくこれまで紙媒体の電話帳(タウンページ)を発行してきたノウハウもございますので、適切なPR手段や集客に関することなど、Webマーケティング全般についてご相談いただけます。
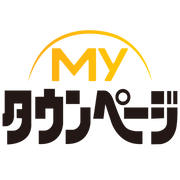
他にも経営の専門家(経営コンサルタント、起業コンサルタント(R)、ファイナンシャルプランナー、(CFP(R)、一級ファイナンシャル・プランニング技能士)、中小企業診断士、司法書士、行政書士、税理士、特定社会保険労務士等の資格保有者)に相談できる経営相談先紹介サービス※2、Webマーケティングや経営に役立つ新鮮かつ正確な情報をわかりやすく解説したコラム・動画コンテンツなど、充実の特典をご利用いただけます。
無料会員登録をいただくだけで、ビジネスオーナーさまのお仕事の強い味方になりますので、まずはお気軽にご登録ください!
※1 相談時間は1回30分までで、利用可能回数は1会員につき月1回まで
※2 相談時間は1回30分までで、利用可能回数は1会員につき月3回まで
Myタウンページ会員登録は
簡単ステップ!
※iタウンページに店舗・企業の掲載がない場合は、こちらからお問い合わせください。
・GA4、GoogleAnalytics4は、Google LLCの登録商標または商標です。